今日は「駒沢大学落語くらぶ 桂文雀 真打昇進落語会」にお邪魔してきました。

出演者は三遊亭遊馬師匠、神田愛山先生、桂竹丸師匠、桂文雀師匠。
この豪華出演陣で無料。お得すぎ。
遊馬師匠はこの間鹿鳴家吉遊さんから聞かせていただいた「家族ドライブの猿」の小噺もやってくれたので、おぉこれか!と、個人的に嬉しかったです。
かなりウケてましたね~
枕、小噺としっかりきっちりと間をコントロールしながら会場の空気を作っていく感じで、凄いなと思いました。
次に上がったのが講談の神田愛山先生。
僕は初めて講談を聴いたのですが、講談ってもうちょっと難しくてわからないようなところもあるってイメージ持ってましたが、全然そうではなく、クスグリなんかもガンガン入ってくるしかなり面白く聞きやすかったです。
演目は「和田平助政勝 鉄砲切り」
講談も面白く聞きやすい、ほとんど落語と変わらないです。
違うところといえば前に机があって張り扇を使う、でもそれは上方の落語も似た感じがあるし、よく言われる、落語は登場人物の会話で描写し、講談は文での描写、事象を外から見た描写って感じで表現するといわれたりしますが、落語はかなり自由度が高いので演目によっては完全に講談調の物もあるような気がするし、ではどこが違うのかといえば
実際の一番大きな違いというのは演目にとてもわかりやすい明確な教訓があるって事なんじゃないかな、と思いました。今回の演目では「卑怯はダメ」みたいな。
そういった難しくなりがちないわば教科書を誰にでも面白おかしく聴かせてしまう、というところが講釈師の凄さがあるわけで。
だから講釈師の敬称は師匠ではなく先生なのだそうですよ。
仲入りをはさんで披露口上があり、その後は桂竹丸師匠。
いやぁ凄かった!
色々凄かったけど僕は動きが新鮮でした。
肩というか体の向きを左右に展開しつつ、首の上下の位置はほぼ通常通りって感じ?
かなり動きを大きく表現できるし、竹丸師匠はきっと直接会場のお客さんに聴かせようって表現なんじゃないでしょうか、普通より目線がちょっと下のほうで直接客に語るような感じだし、そして肩の向きを大きく変えていくことで右端から左端と、お客全員に正面を見せて語りかけようっていう。
色々な工夫、演じ方があるものだな~と勉強になりました。
しかし竹丸師匠、爆笑でした。
僕は表札の小噺でめちゃくちゃハマりました。
竹丸師匠も「えぇそんなにうけるか?!」と困ったかもしれないくらい面白かったです。
最後に上がったのが主役の文雀師匠。
やはり良いですね~細かいところまでホントに良く表現されていて、相変わらず良く練られた良い落語って感じです。
演目は季節に合わせて「お化け長屋」
導入部が僕の聴いた事のある型と違っていたので最初お化け長屋と気がつきませんでした。
短くまとめる為の工夫なのかな?
木兵衛と訪ねてくる2人の客の、3人の対比がキッチリと、そして小気味良いリズム感が良かったな~
話の全体の波みたいのの構成というか作り方がいいですよね。
そうそう、今日会場でチラシもいくつかもらったんですが、その中に
「第一回 桂文雀独演会」のチラシが!

夏らしく、そして個人的に僕が好きな酢豆腐と千両みかん!そしてお約束のように一つは必ず珍しい系の噺で女給の文。
しかもゲストが文生師匠じゃないですか!!
こいつは楽しみすぎる!!

出演者は三遊亭遊馬師匠、神田愛山先生、桂竹丸師匠、桂文雀師匠。
この豪華出演陣で無料。お得すぎ。
遊馬師匠はこの間鹿鳴家吉遊さんから聞かせていただいた「家族ドライブの猿」の小噺もやってくれたので、おぉこれか!と、個人的に嬉しかったです。
かなりウケてましたね~
枕、小噺としっかりきっちりと間をコントロールしながら会場の空気を作っていく感じで、凄いなと思いました。
次に上がったのが講談の神田愛山先生。
僕は初めて講談を聴いたのですが、講談ってもうちょっと難しくてわからないようなところもあるってイメージ持ってましたが、全然そうではなく、クスグリなんかもガンガン入ってくるしかなり面白く聞きやすかったです。
演目は「和田平助政勝 鉄砲切り」
講談も面白く聞きやすい、ほとんど落語と変わらないです。
違うところといえば前に机があって張り扇を使う、でもそれは上方の落語も似た感じがあるし、よく言われる、落語は登場人物の会話で描写し、講談は文での描写、事象を外から見た描写って感じで表現するといわれたりしますが、落語はかなり自由度が高いので演目によっては完全に講談調の物もあるような気がするし、ではどこが違うのかといえば
実際の一番大きな違いというのは演目にとてもわかりやすい明確な教訓があるって事なんじゃないかな、と思いました。今回の演目では「卑怯はダメ」みたいな。
そういった難しくなりがちないわば教科書を誰にでも面白おかしく聴かせてしまう、というところが講釈師の凄さがあるわけで。
だから講釈師の敬称は師匠ではなく先生なのだそうですよ。
仲入りをはさんで披露口上があり、その後は桂竹丸師匠。
いやぁ凄かった!
色々凄かったけど僕は動きが新鮮でした。
肩というか体の向きを左右に展開しつつ、首の上下の位置はほぼ通常通りって感じ?
かなり動きを大きく表現できるし、竹丸師匠はきっと直接会場のお客さんに聴かせようって表現なんじゃないでしょうか、普通より目線がちょっと下のほうで直接客に語るような感じだし、そして肩の向きを大きく変えていくことで右端から左端と、お客全員に正面を見せて語りかけようっていう。
色々な工夫、演じ方があるものだな~と勉強になりました。
しかし竹丸師匠、爆笑でした。
僕は表札の小噺でめちゃくちゃハマりました。
竹丸師匠も「えぇそんなにうけるか?!」と困ったかもしれないくらい面白かったです。
最後に上がったのが主役の文雀師匠。
やはり良いですね~細かいところまでホントに良く表現されていて、相変わらず良く練られた良い落語って感じです。
演目は季節に合わせて「お化け長屋」
導入部が僕の聴いた事のある型と違っていたので最初お化け長屋と気がつきませんでした。
短くまとめる為の工夫なのかな?
木兵衛と訪ねてくる2人の客の、3人の対比がキッチリと、そして小気味良いリズム感が良かったな~
話の全体の波みたいのの構成というか作り方がいいですよね。
そうそう、今日会場でチラシもいくつかもらったんですが、その中に
「第一回 桂文雀独演会」のチラシが!

夏らしく、そして個人的に僕が好きな酢豆腐と千両みかん!そしてお約束のように一つは必ず珍しい系の噺で女給の文。
しかもゲストが文生師匠じゃないですか!!
こいつは楽しみすぎる!!


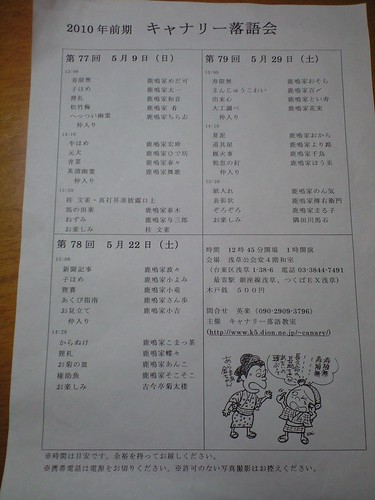

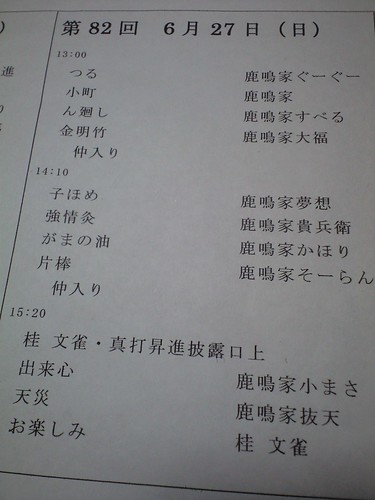

最近のコメント