その他熱い?系の最近のブログ記事
Tweet
川口屋のちくわぶはもちろん、三益酒店のごぼうビール、中川屋の万年筆、他多数の北区民に選ばれた名品が登場。
以下転載
区民オススメのこだわりの逸品が北とぴあに勢揃いします。
北区の名品に選ばれた店舗・企業による展示・即売、そ の他、北区の名品が当たる抽選会も実施します。


参考リンク http://meihin.ichi2010.info/
http://meihin.ichi2010.info/sanka.html
http://www.city.kita.tokyo.jp/docs/event/531/053192.htm
http://www.city.kita.tokyo.jp/docs/digital/542/atts/054259/attachment/attachment.pdf
この日は滝野川体育館でわんぱく相撲が開催されるので、僕はおそらくそっちの手伝いにまわるかと思いますが、、手がすいたら名品のほうもチラッと見に行ってみようかな。
以下転載
| イベント名: | 北区名品市2010 |
|
||
| 日時: | 2010年05月22日(土) / 2010年05月23日(日) | |||
| 10時00分 ~
18時00分 |
||||
| 最終23日は 17時まで | ||||
| 場所: | 北とぴあ 地下展示ホール外 〒 114-8503 東京都北区王子1-11-1 TEL: 03 -5390 -1105 JR・地下鉄南北線王子駅徒歩2 分 ※JR京浜東北線王子駅北口改札 徒歩2分 ※地下鉄南北線王子駅5番出口 徒歩2分 http://www.kitabunka.or.jp/data/sisetu/map/map001.htm | |||
| 主催: | 北区 | |||
| 協賛: | 北区名品の会 | |||
| 後援: | 東京商工会議所北支部、北区商店街連合会、 北産業連合会、王子法人会、王子青色申告会、北区しんきん協議会 | |||
区民オススメのこだわりの逸品が北とぴあに勢揃いします。
北区の名品に選ばれた店舗・企業による展示・即売、そ の他、北区の名品が当たる抽選会も実施します。


参考リンク http://meihin.ichi2010.info/
http://meihin.ichi2010.info/sanka.html
http://www.city.kita.tokyo.jp/docs/event/531/053192.htm
http://www.city.kita.tokyo.jp/docs/digital/542/atts/054259/attachment/attachment.pdf
この日は滝野川体育館でわんぱく相撲が開催されるので、僕はおそらくそっちの手伝いにまわるかと思いますが、、手がすいたら名品のほうもチラッと見に行ってみようかな。
物事がうまくいかないとき、たまにそういうことがあるとき
自分の歩いている道がずっと上り坂のように思えるとき
心配事があって少し気が沈んだとき
必要なら休みなさい、でも諦めてはいけない
だって人生は、山あり谷ありで予測のつかないものだから
誰もがそのことにときとして気がつく
それにゴールはしばしば思っている以上に近くにあって、人を惑わせることがある
敗者はたいていすでに諦めている
せっかく勝者のカップを手にできるときに
彼はようやくのことで気づく、夜が訪れるときに
自分が黄金のすぐ近くにいたことに
成功は失敗と裏表
疑心暗鬼のすぐ向こうにある
だからどん底のときこそしがみつけ
物事がうまくいかないときは諦めるときではない
ダン・バートン氏が子供の頃に母から教わり覚えた詩の一つ。
うーん実にその通りだと思いますわ。
人生、信念をもって決して諦めることなく生きたいですねぇ
図書館で「虫はごちそう」という本をみかけ、なんとなく読んだんですが。
なかなかに素晴らしい内容でした。
もともと僕は子供の頃から、昆虫博士を目指してみたり、ボーイスカウトやったりでサバイバルの本なんか読んで(サバイバルの本には昆虫食についてものっていた)そういうのに抵抗がないというより興味をもっていたから余計かもしれませんが、いやいやとても勉強になりました。
この本はただ単に昆虫食の話というわけではなく、昆虫食から地理学について迫るような内容で、それを小学生くらいの子にもわかりやすく表現しているわけです。
昆虫食というと現代の多くの日本人からすればゲテモノ食いみたいに感じるかもしれませんが、人類にとってとても自然な食文化であるわけで、今の日本人の感覚のほうがちょっとずれてしまっているのかもしれません。イナゴをはじめ日本人も昆虫食が盛んだった(いや今も地方では普通なのかな?)わけです。
ま、そんな地理学的視点でもとても勉強になった。と、いってもやはり興味は昆虫食になりますね。
この本見ているとなんでもホントにウマそうなんです。
蜂の子なんかは有名で、普通に僕も食べてみたい食材ですが
僕がこの本で一番興味を持った、食ってみたいと思ったのが「テッポウムシ」
つまりはカミキリムシの幼虫なんですが、これはネットで調べてみてもかなりウマい物らしく、最近ではあまり口にする機会がすくない「幻の美食食材」みたいです。
「虫はごちそう」から抜粋
・・・・かつて炊事や暖房のための燃料に薪が使われていた時代、木を伐り割ると中からころころ出てきたのだった。山村各地ではよく食べられていた。村人たちは、それを取り出して火であぶると「ひゅーっと伸びてな」とうれしそうに当時を思い出し、「あれはうまかったなぁ」と遠くを見ながら語っていた。元気になるからといって、子供によく食べさせていたそうだ。だれもがおいしいと言っていたカミキリムシの幼虫。時代が変わり薪が使われることはとても少なくなり・・・・
↓テッポウムシを食べるおじさん。かなりウマそう。
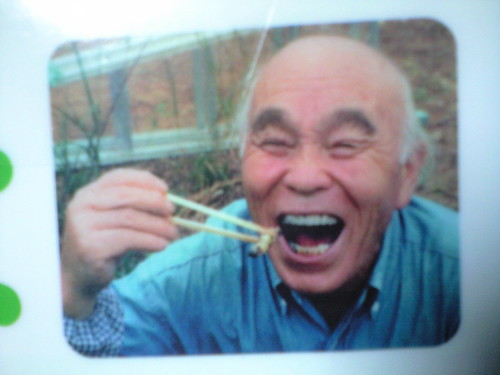
川口屋で一緒に働いてる人が群馬出身の人だったので聞いてみたら、やはり上記の通り食べていたそう。
50代以降の山間部出身の方なら大抵普通に食べているんじゃないかな?ってゆーか蜂の子のように大量にとれないから流通しないけど、いまでも山間部ではたべてるんじゃないか?
まぁなにしろとても「食ってみたい」わけです。
もしかしたら釣具屋とかで餌として売ってたりするかもな、もし売ってたら一度試食会をしてみないとな。
そういえば胡蝶はすっぽんのとき参加できなかったから、そのときには是非胡蝶にも食べさせてあげることにしよう。いやむしろ胡蝶にはこっそり食わせよう。あぁ楽しい。
↓昆虫食についての参考リンク。なかなか面白いので必見です。
昆虫料理を楽しむ http://musikui.exblog.jp/2899724/
虫を食べるはなし http://www.afftis.or.jp/konchu/hanasi/index.htm
なかなかに素晴らしい内容でした。
もともと僕は子供の頃から、昆虫博士を目指してみたり、ボーイスカウトやったりでサバイバルの本なんか読んで(サバイバルの本には昆虫食についてものっていた)そういうのに抵抗がないというより興味をもっていたから余計かもしれませんが、いやいやとても勉強になりました。
この本はただ単に昆虫食の話というわけではなく、昆虫食から地理学について迫るような内容で、それを小学生くらいの子にもわかりやすく表現しているわけです。
昆虫食というと現代の多くの日本人からすればゲテモノ食いみたいに感じるかもしれませんが、人類にとってとても自然な食文化であるわけで、今の日本人の感覚のほうがちょっとずれてしまっているのかもしれません。イナゴをはじめ日本人も昆虫食が盛んだった(いや今も地方では普通なのかな?)わけです。
ま、そんな地理学的視点でもとても勉強になった。と、いってもやはり興味は昆虫食になりますね。
この本見ているとなんでもホントにウマそうなんです。
蜂の子なんかは有名で、普通に僕も食べてみたい食材ですが
僕がこの本で一番興味を持った、食ってみたいと思ったのが「テッポウムシ」
つまりはカミキリムシの幼虫なんですが、これはネットで調べてみてもかなりウマい物らしく、最近ではあまり口にする機会がすくない「幻の美食食材」みたいです。
「虫はごちそう」から抜粋
・・・・かつて炊事や暖房のための燃料に薪が使われていた時代、木を伐り割ると中からころころ出てきたのだった。山村各地ではよく食べられていた。村人たちは、それを取り出して火であぶると「ひゅーっと伸びてな」とうれしそうに当時を思い出し、「あれはうまかったなぁ」と遠くを見ながら語っていた。元気になるからといって、子供によく食べさせていたそうだ。だれもがおいしいと言っていたカミキリムシの幼虫。時代が変わり薪が使われることはとても少なくなり・・・・
↓テッポウムシを食べるおじさん。かなりウマそう。
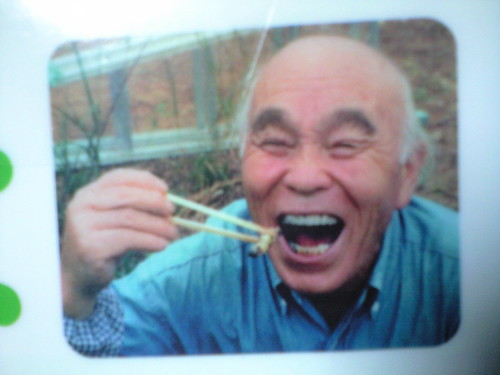
川口屋で一緒に働いてる人が群馬出身の人だったので聞いてみたら、やはり上記の通り食べていたそう。
50代以降の山間部出身の方なら大抵普通に食べているんじゃないかな?ってゆーか蜂の子のように大量にとれないから流通しないけど、いまでも山間部ではたべてるんじゃないか?
まぁなにしろとても「食ってみたい」わけです。
もしかしたら釣具屋とかで餌として売ってたりするかもな、もし売ってたら一度試食会をしてみないとな。
そういえば胡蝶はすっぽんのとき参加できなかったから、そのときには是非胡蝶にも食べさせてあげることにしよう。いやむしろ胡蝶にはこっそり食わせよう。あぁ楽しい。
↓昆虫食についての参考リンク。なかなか面白いので必見です。
昆虫料理を楽しむ http://musikui.exblog.jp/2899724/
虫を食べるはなし http://www.afftis.or.jp/konchu/hanasi/index.htm







最近のコメント