図書館で「虫はごちそう」という本をみかけ、なんとなく読んだんですが。
なかなかに素晴らしい内容でした。
もともと僕は子供の頃から、昆虫博士を目指してみたり、ボーイスカウトやったりでサバイバルの本なんか読んで(サバイバルの本には昆虫食についてものっていた)そういうのに抵抗がないというより興味をもっていたから余計かもしれませんが、いやいやとても勉強になりました。
この本はただ単に昆虫食の話というわけではなく、昆虫食から地理学について迫るような内容で、それを小学生くらいの子にもわかりやすく表現しているわけです。
昆虫食というと現代の多くの日本人からすればゲテモノ食いみたいに感じるかもしれませんが、人類にとってとても自然な食文化であるわけで、今の日本人の感覚のほうがちょっとずれてしまっているのかもしれません。イナゴをはじめ日本人も昆虫食が盛んだった(いや今も地方では普通なのかな?)わけです。
ま、そんな地理学的視点でもとても勉強になった。と、いってもやはり興味は昆虫食になりますね。
この本見ているとなんでもホントにウマそうなんです。
蜂の子なんかは有名で、普通に僕も食べてみたい食材ですが
僕がこの本で一番興味を持った、食ってみたいと思ったのが「テッポウムシ」
つまりはカミキリムシの幼虫なんですが、これはネットで調べてみてもかなりウマい物らしく、最近ではあまり口にする機会がすくない「幻の美食食材」みたいです。
「虫はごちそう」から抜粋
・・・・かつて炊事や暖房のための燃料に薪が使われていた時代、木を伐り割ると中からころころ出てきたのだった。山村各地ではよく食べられていた。村人たちは、それを取り出して火であぶると「ひゅーっと伸びてな」とうれしそうに当時を思い出し、「あれはうまかったなぁ」と遠くを見ながら語っていた。元気になるからといって、子供によく食べさせていたそうだ。だれもがおいしいと言っていたカミキリムシの幼虫。時代が変わり薪が使われることはとても少なくなり・・・・
↓テッポウムシを食べるおじさん。かなりウマそう。
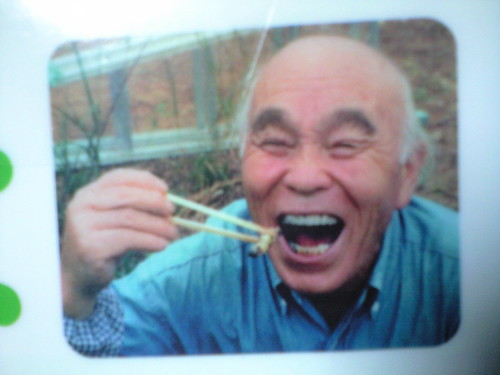
川口屋で一緒に働いてる人が群馬出身の人だったので聞いてみたら、やはり上記の通り食べていたそう。
50代以降の山間部出身の方なら大抵普通に食べているんじゃないかな?ってゆーか蜂の子のように大量にとれないから流通しないけど、いまでも山間部ではたべてるんじゃないか?
まぁなにしろとても「食ってみたい」わけです。
もしかしたら釣具屋とかで餌として売ってたりするかもな、もし売ってたら一度試食会をしてみないとな。
そういえば胡蝶はすっぽんのとき参加できなかったから、そのときには是非胡蝶にも食べさせてあげることにしよう。いやむしろ胡蝶にはこっそり食わせよう。あぁ楽しい。
↓昆虫食についての参考リンク。なかなか面白いので必見です。
昆虫料理を楽しむ http://musikui.exblog.jp/2899724/
虫を食べるはなし http://www.afftis.or.jp/konchu/hanasi/index.htm
なかなかに素晴らしい内容でした。
もともと僕は子供の頃から、昆虫博士を目指してみたり、ボーイスカウトやったりでサバイバルの本なんか読んで(サバイバルの本には昆虫食についてものっていた)そういうのに抵抗がないというより興味をもっていたから余計かもしれませんが、いやいやとても勉強になりました。
この本はただ単に昆虫食の話というわけではなく、昆虫食から地理学について迫るような内容で、それを小学生くらいの子にもわかりやすく表現しているわけです。
昆虫食というと現代の多くの日本人からすればゲテモノ食いみたいに感じるかもしれませんが、人類にとってとても自然な食文化であるわけで、今の日本人の感覚のほうがちょっとずれてしまっているのかもしれません。イナゴをはじめ日本人も昆虫食が盛んだった(いや今も地方では普通なのかな?)わけです。
ま、そんな地理学的視点でもとても勉強になった。と、いってもやはり興味は昆虫食になりますね。
この本見ているとなんでもホントにウマそうなんです。
蜂の子なんかは有名で、普通に僕も食べてみたい食材ですが
僕がこの本で一番興味を持った、食ってみたいと思ったのが「テッポウムシ」
つまりはカミキリムシの幼虫なんですが、これはネットで調べてみてもかなりウマい物らしく、最近ではあまり口にする機会がすくない「幻の美食食材」みたいです。
「虫はごちそう」から抜粋
・・・・かつて炊事や暖房のための燃料に薪が使われていた時代、木を伐り割ると中からころころ出てきたのだった。山村各地ではよく食べられていた。村人たちは、それを取り出して火であぶると「ひゅーっと伸びてな」とうれしそうに当時を思い出し、「あれはうまかったなぁ」と遠くを見ながら語っていた。元気になるからといって、子供によく食べさせていたそうだ。だれもがおいしいと言っていたカミキリムシの幼虫。時代が変わり薪が使われることはとても少なくなり・・・・
↓テッポウムシを食べるおじさん。かなりウマそう。
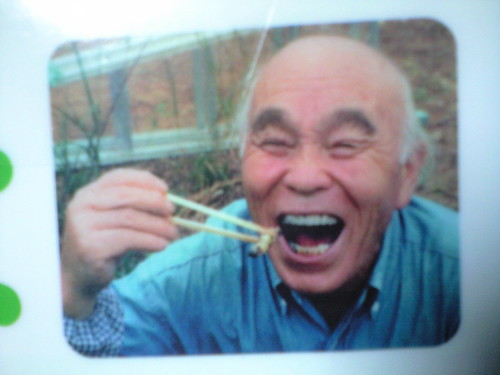
川口屋で一緒に働いてる人が群馬出身の人だったので聞いてみたら、やはり上記の通り食べていたそう。
50代以降の山間部出身の方なら大抵普通に食べているんじゃないかな?ってゆーか蜂の子のように大量にとれないから流通しないけど、いまでも山間部ではたべてるんじゃないか?
まぁなにしろとても「食ってみたい」わけです。
もしかしたら釣具屋とかで餌として売ってたりするかもな、もし売ってたら一度試食会をしてみないとな。
そういえば胡蝶はすっぽんのとき参加できなかったから、そのときには是非胡蝶にも食べさせてあげることにしよう。いやむしろ胡蝶にはこっそり食わせよう。あぁ楽しい。
↓昆虫食についての参考リンク。なかなか面白いので必見です。
昆虫料理を楽しむ http://musikui.exblog.jp/2899724/
虫を食べるはなし http://www.afftis.or.jp/konchu/hanasi/index.htm




最近のコメント